FACULTY 教員検索

教員検索
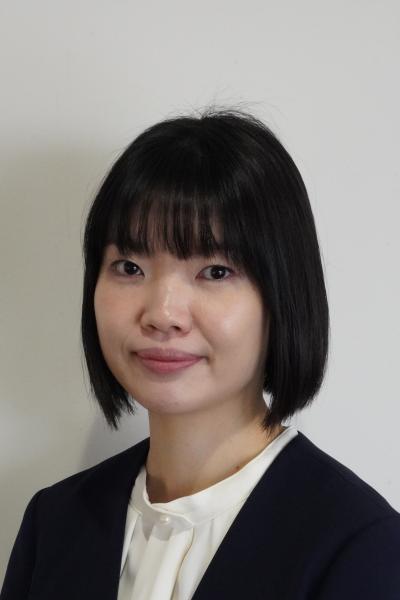
| 教員氏名 | 戸江 真以 |
|---|---|
| ローマ字 | TOE Mai |
| 所属学科 | 子ども健康学科 |
| 職名 | 准教授 |
| 研究室 | 弘明館4階(A418) |
| メールアドレス | m-toe@fains.jp |
| 主要担当授業科目 | 音楽の基礎、子どもの表現Ⅰ、音楽(器楽) |
| 専門分野 | 幼児の音楽教育、ピアノ教育 |
| オフィスアワー | 火曜日3限 |
| 最終学歴 | 広島大学大学院教育学研究科博士課程後期文化教育開発専攻音楽文化教育学分野修了 |
|---|---|
| 取得学位 | 博士(教育学) |
| 職歴 | 比治山大学現代文化学部子ども発達教育学科非常勤講師(2018年1月まで) 広島大学教育室教育部附属学校支援グループ契約一般職員(附属三原幼稚園教諭補佐)(平成30年3月まで) 福岡女学院大学人間関係学部子ども発達学科契約講師(令和5年3月まで) 福岡女学院大学人間関係学部子ども発達学科非常勤講師(令和6年3月まで) 佐賀女子短期大学こども未来学科保育コース准教授(令和7年3月まで) |
| 所属学会名 | 日本音楽教育学会、音楽学習学会、音楽教育史学会、日本保育学会、日本乳幼児教育学会、中国四国教育学会、日本音楽表現学会、身体運動文化学会 |
| 教育研究社会活動 | 2024年11月 鳥栖市児童厚生員等研修会 講師 2025年 2月 佐賀県母子寡婦福祉連合会保育サポーター(家庭生活支援員)養成研修 講師 |
| 研究活動の概要 | 研究活動(1) ■研究題目 和田実の『音楽的遊戯』論(単著) ■研究の要旨 和田実(1876-1954)は、明治後期から昭和期にかけて活躍した幼児教育者である。幼児期における唱歌教育ないし音楽教育に関する論文を雑誌に寄稿するなど、幼児教育者のなかでも、音楽に造詣が深い人物であると考えられる。和田は、著書『実験保育学』(1932)において、「聞かせる音楽」「歌はせる唱歌」「舞踊」の3つを「音楽的遊戯」と呼び、なかでも音楽を聴かせることを重要視している。本稿では、この「音楽的遊戯」構築の変遷を明らかにした。 ■研究成果の報告 広島大学教育学研究科『音楽文化教育学研究紀要』、第29号、pp.63-70。2017年3月。
研究活動(2) ■研究題目 印牧季雄の舞踊教育観―舞踊教育の目的と教材に着目して―(単著) ■研究の要旨 本研究は印牧季雄(1899-1983)の舞踊教育観を明らかにすることを目的とする。対象とする主な文献は,『スクールダンス』(1924),井上徳雄と共著の『学校遊戯振付の理論と実際』(1931)、『学校舞踊理論より創作へ』(1933)、丸岡嶺と共著の『学校舞踊創作の理論と実際』(1949)である。また、適宜舞踊教材集の緒言を参照する。検討の結果、第一に、子どもが興味をもって、楽しく活動することである。それまでの「無味乾燥」な体操教育を否定し、その解決策としての舞踊をアピールしていることが明らかとなった。第二に、印牧の舞踊教育観は、当時のあらゆる教育思想から影響を受けていることである。具体的には、知識偏重型教育への批判、芸術教育運動、童謡運動、リトミック思想等である。教育界に新しい思想が数多く入り込んできたが、それを印牧は積極的に採用したことが、彼の言説の随所に確認できる。 ■研究成果の報告 『広島大学大学院教育学研究科紀要 第二部(文化教育開発関連領域)』、第68号、pp.299-306。2019年12月。
研究活動(3) ■研究題目 保育者・小学校教員養成課程におけるピアノ学習の現状と課題(1)―動機づけの視点から―(共著) ■研究の要旨 赤間健一氏との共著。「1.研究の背景と目的」、「4.考察」を担当。本研究では、一斉授業の形態をとるピアノ学習環境において学習者がどのように動機づけられピアノ学習に取り組んでいるのかを調査し、養成校におけるピアノ学習の現状と課題を明らかにする。女子大学の学生108名が調査に参加した。藤田(2010)の自律性支援の認知、心理的欲求、体育授業用動機づけ尺度をもとにピアノ学習に合うように項目を作成し、自律性支援の認知、心理的欲求、動機づけを測定する尺度を使用した。その結果、学生の大学入学前までのピアノ経験が動機づけに影響し、ネガティブなものは未経験群が高く、未経験群は、自律性支援よりも関係性欲求を満たしていた。今後の課題として、学生同士が関係性を重要視していることを活かす学習支援を検討することである。 ■研究成果の報告 『福岡女学院大学紀要人間関係学部』、第21号、pp.1-7。2020年3月。
研究活動(4) ■研究題目 保育者・小学校教員養成課程におけるピアノ学習の現状と課題(2)―ピアノ演奏技術の視点から―(共著) ■研究の要旨 赤間健一氏との共著。本研究は、「保育者・小学校教員養成課程におけるピアノ学習の現状と課題(1)」をもとに、未経験軍と経験軍のそれぞれ心理的欲求、動機づけ、ピアノ学習における技術面との因果関係を調査した。その結果、未経験軍において運指を考えることに対する意識が低いこと、ピアノの技能を修得することの意義を感じているほど読譜に取り組むことが明らかとなった。経験軍においても運指を考えることにネガティブな結果を得た。また、経験軍は、学生同士の関係性が満たされるほど読譜に取り組むことが明らかとなった。 ■研究成果の報告 『福岡女学院大学紀要人間関係学部』、第21号、PP.9-14。2020年3月。
研究活動(5) ■研究題目 印牧季雄による「リズム生活」の体験を重要視した学校舞踊論の歴史的意義-マリー・ヴィグマンの理論との比較検討をとおして-(単著) ■研究の要旨 本研究では、舞踊教育家である印牧季雄による学校舞踊論の歴史的意義を彼の師であるドイツの舞踊家マリー・ヴィグマンの論との比較検討をとおして明らかにした。その結果、①印牧は、学校教育の外で興った文化である童謡舞踊を、学校舞踊の名称を用いて、教育活動を通じて教育分野に浸透させたこと、②印牧の学校舞踊論は、模倣が主流であった遊戯教育が行なわれていたころより、マリー・ヴィグマンのダンスの理念と重なる自己表現を目指した先駆的な見解を示していたことが明らかとなった。歴史的意義として、印牧の教育活動が戦後の学校教育における「創作ダンス」導入の一助となり、印牧の学校舞踊論の実現が叶ったことが指摘される。 ■研究成果の報告 『音楽教育史研究』、第25号、pp.3-14。2021年3月。 |

